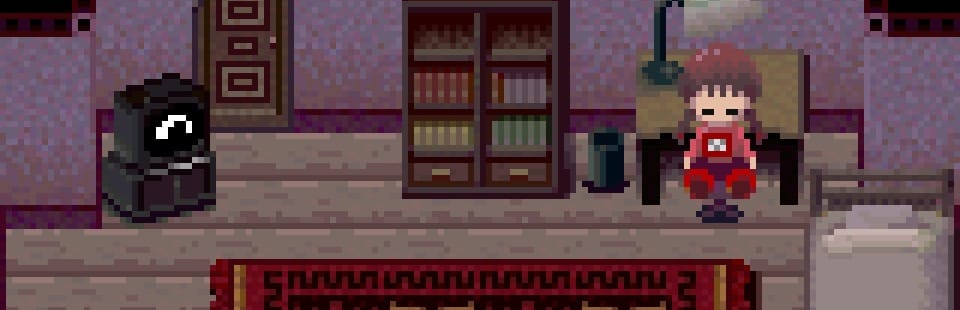Magic Wand, Dismal Anhedonia Land
2010年代中盤から出られなさそうで怖い

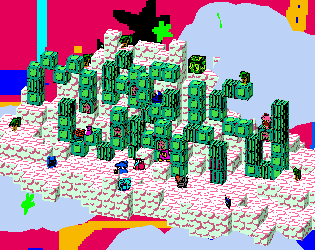

聖剣LoMをやっていたとき、当時は普通に近所の家電量販店で売っていたプロアクションリプレイを使って、覚えたてのインターネットで調べた武器強化のレシピを再現し、攻撃力1000近いヌンチャクを作ってはしゃいでいた。一方でストーリーの理解はあいまいだった。特にエスカデ編などは意味が解っていなかった。行間を読めなかったり、キャラクターの感情の機微を理解できないのもあったが、子供だった自分にはそもそも文章や単語そのものがあまり読めていなかった。
それでも、カペラとディドルの一連のクエストの最後、奈落の外で星空を眺めながらなんとなくいい感じの会話をしていたり、石になった元カレを救おうとするリュミヌーの心境とか、なんか妙に心に残った瞬間がある。それがメインストーリー上の重要な要素だったかどうかは覚えていない。
このゲームは There are fragments of plot relayed out of sequence but you do not care because the music and the colours. When the narrative peaks, you say "Good!" and then forget it.
と自ら説明している。この説明の通り、断片的な昔のJRPG(たぶんファイナルファンタジー6)を思い出しているときの脳をスキャンした結果を、そのまま映し出したようなゲームに感じた。
何も理解しないまま急に始まる戦闘、知らないキャラクターや地名がどんどん出てくる。BGMや背景画像、マップチップが変わったのに気づいて、「なんかストーリーが進んでるっぽいな」と思う。さっきスキップしたセリフにヒントがあったかも、説明書になにか書かれていた気がする。ストーリーも佳境になり、様変わりしたワールドマップを探索しているとき、ずっと気にかかっていた収集アイテムの最後の一つが見つかる。そういえば、そこでプレイするの止めちゃってラスボス倒してなかったかもしれない。
あまり語られない方の「名作ゲーム」の体験を再生しているようだった。当時からそういうセルフパロディをやっているゲームはあった気もするけど、20年くらいたってだいぶ熟成された結果、批判的視点が薄れて嫌味さが懐かしさに変換されている気がした。
何周もしないと気づかないストーリー上の伏線や、戦闘バランスの絶妙さなど、細部の作りこみが名作を名作足らしめている所以という話はある。でも、完全に自分の視点で見たときに、そのゲームが名作だからプレイしていたというより、ゲーム売り場や家電量販店のチラシで見かけたからそれを買っただけで、べつに中身はなんでもよかったんじゃないか。
当時同じゲームをプレイした人間が、情熱をもってそのゲームのすばらしさを語っているのを聞くと、もしかしたら自分は親戚のおっさんが作った謎のハックロムをやっていたのかもしれないという気持ちになる。誰かの情念がこもった語りの方が世間では話題になりやすいので、昔はハマってたけど今はそれほどでもないかもという作品に対して、平熱で振り返る機会はあまりない。
『Dismal Anhedonia Land』をやってこういう話をもっと聞きたいと思った。