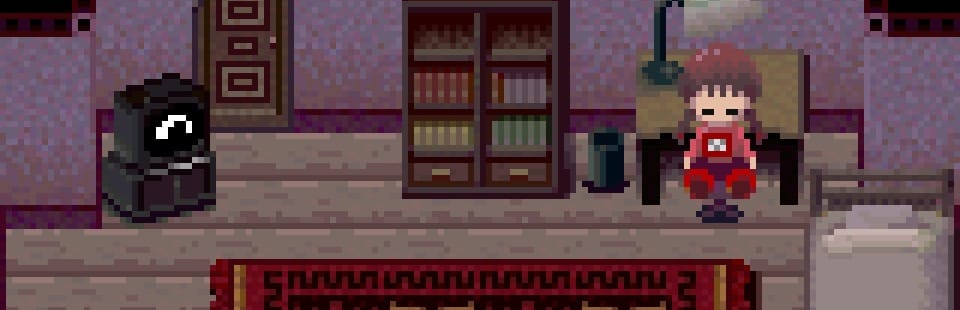Peaks of Yore
流行らなさそう

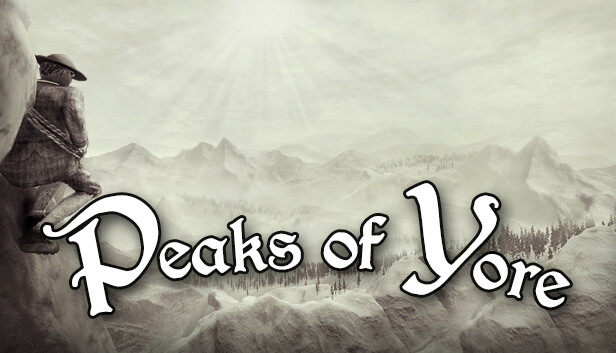
自分が知っている範囲での「登山」ゲームの特徴は、単純な入力、感覚的な操作性、そして制限されたチェックポイントの三つ。入力が単純(例えばアイテムや特技の使用やコマンド入力がない)だと、小手先の技術や知識でカバーできる部分が少ない。操作が感覚的(例えばアナログスティックでの無段階入力など)なほど、身体的な素質や集中力に大きく依存し、習熟が難しい。そして、チェックポイントの制限により、操作精度の低さを試行回数で補うことができず、途方もない低確率でしか成功できない。大きなリスクを伴う長時間の反復行動によって集中力が削がれ、肝心の難所で失敗する。これを繰り返しながら少しずつ最高到達地点を伸ばしていく。
なぜわざわざ余暇にそんなことをする必要があるのか。しかも何時間もかけて。
「山に、何かいいものでも落ちていると思ったか」と羽生も言っていた気がする。「山に行けば、生き甲斐でも見つかると思ったか」とも。
自分が登山的な性質を持つゲームをやるときも同様で、「配信でウケたい」とか「人に自慢したい」といった即物的な望みを持ってプレイすることを肯定すると、これまで守ってきた無意味な「戒律」を崩すような気持ちになる。かといって、自分の内面の整合性を保つ以外の目的を持ってはいけない、という、なんか修行でもしてんのかってほどにのめり込むこともできない。
自分にあるのは、誰かが崇拝する山頂に登って「こんなのカスみたいなもんですね」と腐し、無意味にしてやりたい、引きずりおろしてやりたいという真のカスの感情だけかもしれない。こんなの所詮ゲームだろ、お前らそれしかやることがないからやっているだけだろ。
しかし、生きているうちに段々と、「もう自分にはこれしかやることが残っていない」という状況に、どんな人間でもなっていく。別にそれは仕事でも家族でも、セールで50円の登山ゲームでも変わらないのかもしれない。宇宙に単一の正しい答えがあるという考えが否定される世界では、人生は長い放浪であり、年齢とともに自己同一性は崩れていく。人間は自由に登山ゲームを遊ぶ存在ではなく、断続的に訪れる「登山ゲームをやらざるをえない時期」に従うだけ。
イシュメールのように世界を持たず、自身のアイデンティティを持たない完璧な存在に近づくため、そこに答えがないことを確認するために登山ゲームをする。自分自身の世界の解釈を確認し、それが誰かと共有されていることが、癒しになるのかもしれない。
このゲームはロープやクランポンなど、さまざまなアイテムの使いようによっては多少の難所は楽に突破できる。アクション自体もそこまで理不尽な難易度ではないわりに、緊張感や圧迫感があったのは、それだけ登山の雰囲気が出ていたせいかもしれない。少しの才能と技術、あとは集中力や体力、そして根気。実際の登山をかなりスケールダウンした形ではあるが、仮想的に体験できるゲームだと思う。
アイテムを使いこなしながら登る面白さはあるが、ロープやクランポンで逐一安全を確保していると、単純な繰り返し作業に時間が割かれる。本当の登山なら落下死を避けるためにそうした作業をおろそかにできないのは当然だが、ゲームとして適度に緊張感を残しながらやるには自分でアイテムの使用を縛る必要があるのかもしれない。それでも、「もうめんどくさいからロープなしでいいや」というときほどジャンプに失敗するのも、現実の事故発生の原因としてありそう。
Solemn Tempest を登っている最中に感じたのは、ただ道が長い、山頂が全然見えない、ずっと同じことの繰り返しという、自分の数少ないリアル登山の記憶とほぼ一致する感覚だった。難しいとか何度もやり直させられるといった種類ではない辛さをゲームで味わったのは久しぶりかもしれない。
正直、自分がプレイした中では、テクニックや知識を得られることはほとんどなく、一人称視点でそこそこ素早く動きながら小さな的を狙うという、プレイヤーの運動能力に大きく依存するゲームに思えた。だから、Solemn Tempest には、一人だけ居残りで体育の授業をやらされているような辛さがあった。
一点、Solemn Tempest で良かったのは、最後の登山シーケンスや山頂でも何の演出もないところだった。あくまで「ただの山」でしかないという設定に忠実で、上で書いたような「山を登ること自体には何の意味もない」という考えも含め、さまざまな解釈を否定しないでいてくれる気がした。