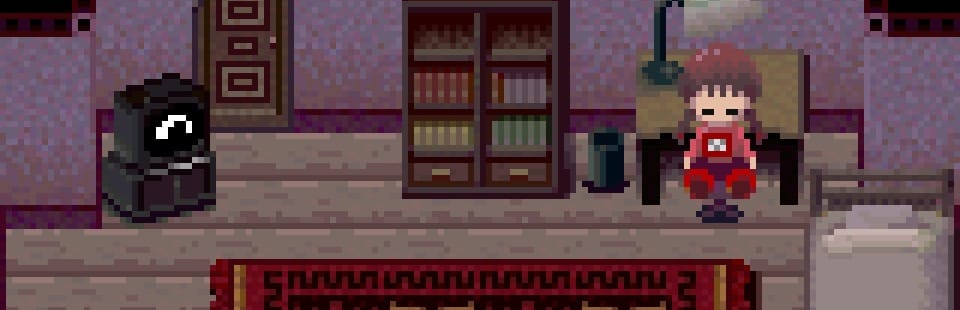PRODUCER 2021
I'v got no qualifications for any of this!


このゲームについて何かを考えようとしたんだけど、開発後記を読んで、そういうのじゃないのかもという気分になった。そもそもゲーム開発者は、ゲームを作って売らなければ生活できないことを意識すると、「なんでこのゲームを作ろうと思ったのか?」という質問に意味なんてない気がしてくる。
もし今自分がやっている仕事について誰かに聞かれたら、この仕事にはこういう必要性があるんですよ、などそれらしいことは答えられるだろうけど、じゃあお前はどう思ってるんだ、と詰められたら、まあめちゃくちゃつまんないと思ってるわけではないし、それなりにやりがいは感じてますけど……みたいにしか答えられない。これは結局、生活の安定と自分の嗜好を天秤にかけて仕事を選択して、そのリスクを取るという行為を避けてきた結果だが、なんでそんなリスクを取らなくちゃいけないんだというわがままなガキがまだ自分の中で幅を利かせている。そして正直そういうガキのことを自分は嫌いになれない。
考えが脱線していると思っていたら、 self actualisation VS rent
をゲーム全体における高次の葛藤としてデザインしようとしたと開発記に書かれていたので、このゲームをやった後、漠然と上で書いたような不安を感じたのは作品の意図通りなのかもしれない。
啓示を受けて旅に出た主人公が、なんか象徴的な感じの様々な事象に出会うところから、現代の聖典のような雰囲気を感じた。世界そのものをすべてこの作品に表現しようとした壮大な計画があった気がする。仕事や生産について主に語っているところから一瞬『アエネーイス』っぽいのかもと思った。自分は『アエネーイス』についてこの講義でしか知らないし、もっと着想を得た元としてしっくりくる作品はありそうだけど。
熱心な仕事と生産への賞賛、それによってもたらされる結果が世界をより良くし、絶対的なボスへの忠誠へと導かれること、そしてそれらがすべてプロパガンダに過ぎない可能性について示唆されている。単純に現代のビジネスにおける価値観がローマ人のそれと近いだけかもしれない。
少なくとも、現代のテキストアドベンチャーとして仕事に対する積極性を持つかどうかはプレイヤーの選択にゆだねられている。そしてその熱量がゲームに対して重要な影響を与えるかというとほとんど変化はない。熱量が多いことで変化するのは作業台でのクラフト関連のクエストだが、結局自分は鍛冶のスキルを得る方法がわからず何も作れなかった。やる気だけあってもスキルを学習する機会がないと何も作ることができないのは、割と残酷に現実的な視点だなと思った。
Biochemist, Mechanic, Dataists三者は仕事に対する熱源の比喩に見えた。Biochemistは自己陶酔的な衝動、Mechanicは劣等感の補償、Dataistsは技術に対する信仰心あるいは狂気。全員、The Growthの跋扈とともにいなくなる。そうした情熱も、ビジネスや技術の成長や競争に追い落とされてドロップアウトしていったように感じた。
最終的にこれらの出来事をすべて計算していたThe Cyborgの仕事をTotoが引き継いで終わらせることになる。終わらせずに逃げることもできる。The Growth に対して抵抗力があったのか、ただの偶然なのか、Totoに白羽の矢が立った理由は明示されない。Totoは「自分には何の資格もない」というが、結局仕事に必要な一番の資格とは、ちょうどいい時にちょうどいい場所にいることなのかもしれない。
全編通して、家族や恋愛の話は一切出てこない。仕事の話だけで、それも具体的な職種についてではなく、構成されているアドベンチャーゲームは珍しい気がする。開発終盤に大幅に要素を削ったとあるので偶然かもしれないが、仕事しか存在しない世界の奇妙さが結果的に強調されている気がした。
第二章の、三つのプロトタイプを手に入れるそれぞれのクエストラインは異なるテーマというかネタがあってうれしかった。でも、こういう謎解きの解法を推理しているとき、脳のどんな部分を使ってるか分からないというか、正直自分は何をしてるんだろうなという気分になることもある。
Bonglordの家では、コップに水を入れたり、シンクに流したり、飲もうとしたり、一旦シンクに置いたり、また持ったり、床に置いたりしていた。なんとなく太古のコマンド入力式のテキストアドベンチャーゲームのパロディなのかもしれないと思った。
Dataistsの住処に行く方法はエレベーターと梯子で二つある(たぶん)。エレベーターを使うには古代のElevator Guardの口にゴミ溜めで殺したLast Ratの死体を詰め込んで、口が動かない内に乗る必要がある(口が動いていると「危ないから使わないで」と怒られてしまうから)。梯子を使うには、なんだっけ、Bonglordの家の床に転がっているハイヒールを拾って、それを履いて梯子を下してたと思う。
こういうめちゃくちゃなノリのギャグは好きなんだけど、最近そういうゲームばっかりやってるせいか、「理解できなさ」を受容できる容量を超えてしまって、全部の感情がゼロになってしまうときがある。
開発記にあるように、こういう謎解き全てに self actualisation VS rent
を寓意化しようとしていたなら、そら頭おかしくもなるよなと思った。
- ゲーム起動時の緞帳が開く演出とか、主人公が普通にシステムメッセージと会話してたりとか、主人公が何者かとか気にせず自分だと思ってやってくれと言う意図を省エネかつ暗黙的に実装しているのは楽しかった。
- 経験値システムはギャグでもあり、マップを行ったり来たりしているときに新しいイベントが起きたのに気づきやすくて結構嬉しい発明だと思った。
- BGMが好き。The Cyborgを探しに行くときの曲がなんかGilla BandのPrefab Castleみたいでよかった。
- なんかここに書くのでいいのかとかそういうのはあるんですけど、このゲームはashi_yuriさんからギフトで頂きました。ありがとうございます。