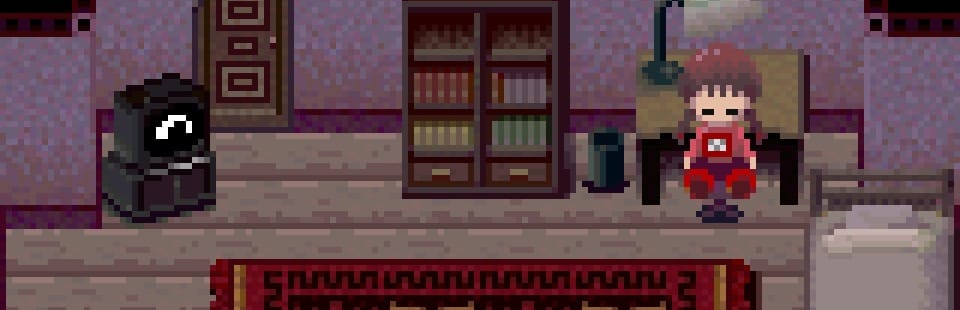スーパードリフトブレード
知識アンロック系とは

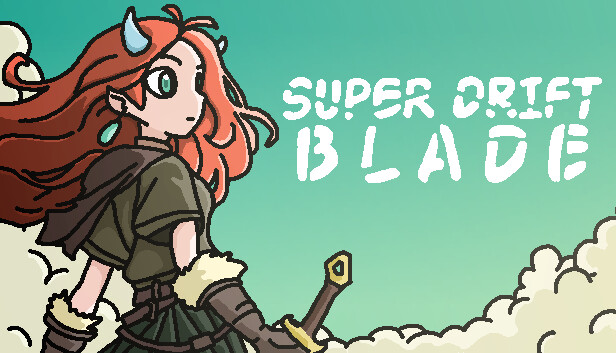
シンプルな謎解きゲームとしてみると相当面白い。ただ、ローグライト風アクション要素が追加されることで、サバイバルホラーによくある、化け物から逃げたり銃を撃ったりなど他のことに気を取られながら謎解きをしなくてはいけないような、そういう印象も持ってしまった。
とはいえ、繰り返し要素もそれほど億劫ではないし、アクション要素も謎解きの妨げになっているわけではない。少なくともあまりやったことないタイプのゲームをやれた気がして面白かった。どこに重きを置いて見るかで評価が変わってきそうなゲームなのかもしれない。
自分は「知識ロック系」としてこのゲームが紹介されているのを見たので、このゲームもそういう目で見ていたんだけど、知識で行動範囲が増えるといっても、色々種類があるなとは思った。
このゲームの謎解きは風景パズルのようにマップやテクスチャから推理する必要はあるけど、得られる情報とそれを適用する箇所は一対一の関係になっている。
『Toki Tori 2』のようにテクニックを覚えるものと、ダイヤル錠の番号を知ることで扉を開けられるようなものも、同じ知識ロック系とかナレッジベースドなどと言われることがあるけど、そうなのか。この呼称は覚える知識の質よりも、覚えた知識で進める場所が増える特性に意識が向いている気がする。質で言うと、テクニックを覚えてやれることが増えるのは、ほぼすべてのゲームがそうなので、それで区別しても意味がないのかも。
でも、新たな知識を得たときに、「そんなことできたんだ!気付かなかった!」と驚きを感じるか、単純に謎解きのヒントを得たと思うかは、個人差はあると思うけど、謎解きの作り方による違いがあったりするんでしょうか。
例えば、すぐに試してみたくなるほど活用することのメリットがわかりやすい、とか。そうだとすると、プレイヤーは事前に「ここに何かありそう」とあたりをつけられる必要がある。すると後から戻ってくることは確定になってどこか焦らされているように感じる。なんか違う気がする。これは違います。
だから、『Leap Year』とか『Animal Well』とか『Outer Wilds』とか(『Toki Tori 2』も)は一つのアクションやアイテム、そして場所に複数の使い道を隠していたのかも。最初の発見である程度進捗を感じさせつつ、その発見に他の秘密を隠すことができるので。何週遅れの気づきかわからないけど。