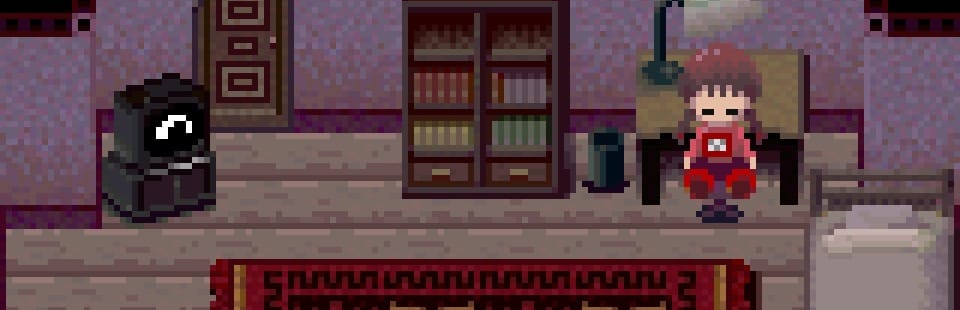What Remains of Edith Finch
ゲームの中で一番好きなゲームがゲームである必要性を疑われている

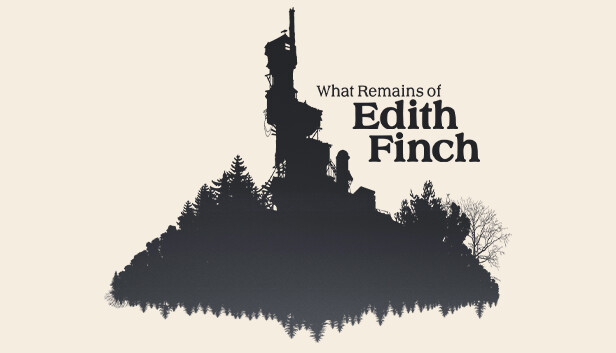
相次いで起こる不運な事故について、それは家族の呪いを迎え撃とうと全力で生き急いだ結果だという物語を一族の人間が信じようとしていることが、恐ろしさのなかにどこか清々しさのようなものを生み出していると思った。例えばカルビンの物語は、実際は単なる強風による事故だったのかもしれないが、今日空を飛ぶと決めたからそうした、と解釈したサムのフィルターを通して見ることで、恐れとともに喜びや誇りが感じられる。自らの早すぎる死期を悟ったエディスも、こうしたフィンチ家の生き様を好意的に解釈したかっただろう。
自分の人生になんらかの物語ないし世界の解釈を当てはめたいと願うとき、それはすなわち「癒し」が必要なときであり、答えを一つに決めることはできない。有り体に言うと、「自分の人生ってなんだったんだ?」となるときには、「これってなんの話だったの?」という物語が必要になる。そういう物語から無理やり何かを見つけようとするのは徒労かどうかで人が喧嘩しているとこを見たい。いや、見たくない。両方の気持ちがある。
物語の内容や人間性とは無関係に、各シーケンスのゲーム中での演出の自分の好み(驚きとか好奇心を煽られる感じとか)Tier表を作ると以下のような感じ。いや実際Lewisだけ飛びぬけて好きで、他は全部同じくらい面白いかったからあんま意味ないかも。
S: Lewis
A: Sam, Molly
B: Gregory, Calvin
C: Walter, Barbara
D: Gus
N/A: Milton
Lewisが生きた22年間の内、少なくとも高校卒業後の最後の4年間はドラッグと空想に耽っていただけとすると陰鬱な人生に聞こえる。しかし、1988年から2010年までのゲームの技術的進歩に合わせてLewisの想像が強固になっていった演出により、人生をかけてクリエイティブな情熱をそれに傾けた不世出の天才に見える。それはあくまで空想の世界に過ぎないことはプレイヤーもEdithもわかっていながら。
一瞬、現実の缶詰工場のロッカーらしき場所に移るが、そこからまた空想の世界に入り現実の世界に帰ってくることなく終わる。空想の世界の楽天的な雰囲気のまま陽気なBGMの音圧が大きくなっていきギロチン台に首を垂れるところは、全ゲームの中でも一番好きな瞬間かもしれない。ゲーム全体を通して言えることだけど、「抽象的で無害なウォーキングシミュレーター」の雰囲気とのギャップを利用して(悪用かもしれないが)衝撃的な現実を表現している感じがある。
このギャップは特にSamの物語で顕著で、『Firewatch』の中盤のような牧歌的な雰囲気のまま、ほとんど何の前触れもなく落下死してしまう。この唐突さがギャグではなく現実の不条理さとして映るのは、これまでの物語やゲーム全体の雰囲気づくりの結果なので個々の物語だけ切り出して語ってもしょうがないかも。あと、『Firewatch』を抽象的で無害とは言えないと思う。
Mollyの物語は、最初にこれがどういうゲームなのかを示しながら、敢えて不可解にさせる役割もある気がする。明らかに自分たちが生きる現実とは違う不条理な物語は、プレイヤーに「信頼できない語り手」の物語から現実で起きたことを推理する必要があると思わせる。また、一番最初にプレイヤーが出会う物語として、これって本当に「怪物」が出てくるようなゲームなの?という疑念も抱かせる。
GregoryとCalvinはどちらもSamの手紙から語られる。このSamの捉え方——目の前の関心事に対してリスクを無視して邁進する性質をフィンチ家の人間が持っていること——はその娘であるDawnに受け継がれていることが、Samの部屋でのEdithの語りや、Dawnの大学卒業後の行動からも示唆されている。また、Samの手紙では同時にBarbaraの葬式についても触れていて、その死が10歳そこそこの二人に影響を与えたのは想像に難くない。
WalterもBarbaraの死に強く影響を受けた一人で、50年以上地下室にこもりその一生を洞窟で過ごした。DawnやSamがとった方法と真逆だが、呪いという致命的だが対処法のないリスクを受容した結果という点では同じかもしれない。BarbaraやMollyなどは、Edithから見るともう過去の話で、内容は恐ろしいがどこか非現実的で不条理なギャグの要素もある。一方で、最近まで生きていた上に現実的で終始暗い雰囲気のWalterの物語は、Edith、そしてプレイヤーを現実へと引き戻す。秘密裏に幽閉されていたWalterの存在が明らかになることで、全ての事件の黒幕など安っぽい真実があるのではという不安がサスペンスになるのは奇妙だった。
Gusの物語は他と比べると淡泊だけど、結婚式のパーティなど誰かの死と関係ない陽気な瞬間や、Samがどんな父親だったのかが垣間見れる。あと、Gusの死に対するDawnの率直な詩が、趣味は全然違うし何考えてるかもわからないけど少なくとも父親に対して同じ不満は抱えている姉弟の距離感が表れていて好きだった。
Miltonは前作からのゲストキャラという感じだけど、こういう外れ値があると家族の呪いも一面的なものでしかないという証拠になるのかもしれない。
- Gregoryの話はある意味一番現実味があって怖かった。事故の現実感ととゲーム中の演出の差という点ではこれが一番すごかったかもしれない。
- Lewisのダンジョンが、トップダウンからクオータービュー、最終的には一人称視点に変わるのは特定の種類のRPGの進歩に沿っているような感じがするけど、Lewis自身の3Dモデルが常に変わらなかったのは単純に開発コストの問題なのかなんだろう。
- びっくり度(?)でいうと、SamとWalterが一番だった。どちらもこの雰囲気から即死することあるんだという感じで、特に初見では何が起きたか分からなかったWalterがすごかった。現実でわからん殺しされたらあんな感じかもしれない。
H.P. ラヴクラフトやエドガー・アラン・ポーに代表される「ウィアード・フィクション」に近づけたかったとか、構造はガブリエル・ガルシア・マルケスの『百年の孤独』に影響を受けた、という話はこのインタビューで知った。ラヴクラフトとかマジックリアリズムとか難易度高そうと思って避けてたけど、読まなくちゃいけないかもしれない。『百年の孤独』もまだ全部読んでない。
The Atlanticの記事(記事まだ読んでないです。これだけのために年80ドル払うの怖くって……)とかで発売当時から議論されてたり、すでに上のインタビューで回答されていることではあるけど、アニメや映画など映像作品として出すんじゃなくで何でゲームなのという話はあるとは思う。こういう話はすでに Wikipedia で "Ludology" vs "narratology" とまとめられているくらい昔からある議論だけど。
これについて完全に自分の視点の話をすると、もう単純にゲームじゃないと、というかコントローラー握ってないと最後まで集中力続かないんだよな。映画やアニメも自分でボタン押さないと次のカットに進まないような仕組みがあったらもっと見れてるような気がする。あと、ゲームになっていることで、こういうウォーキングシミュレーターって大体ほっこりする雰囲気で終わるよなというちょっと舐めが含まれた経験に対する裏切りとかそういう効果も出てきちゃってはいると思う。